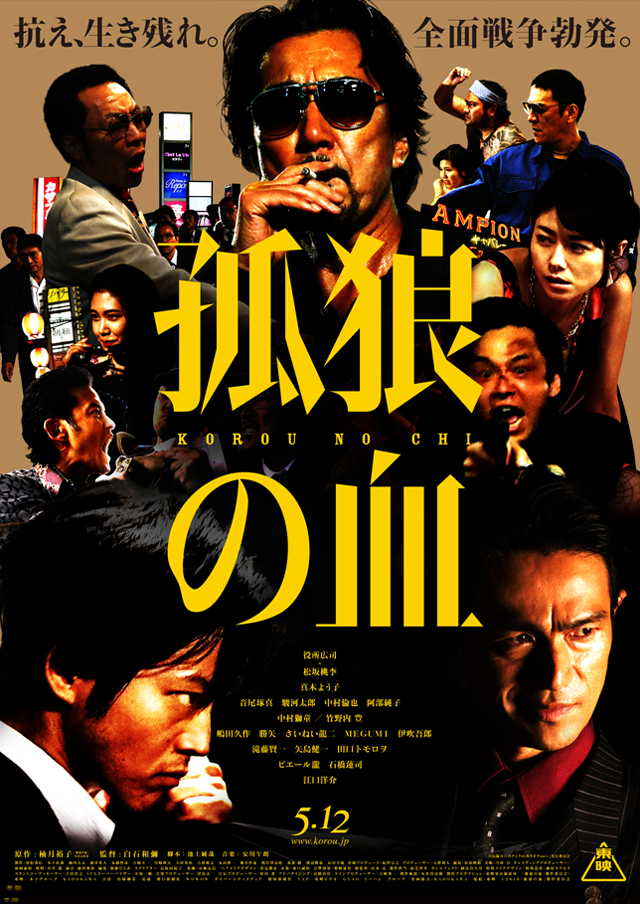解説
世界的冒険家、植村直己の生涯を描く。原作は植村直己、脚本は岩間芳樹と佐藤純彌の共同執筆。監督は「空海」の佐藤純彌。撮影は「人生劇場(1983)」の並木宏之がそれぞれ担当。数々の極地ロケのために当時の一流の登山家が集められ、カメラマンを含む11名の撮影隊が組成された。1985年10月30日、隊員のうち7名ものメンバーがエベレストに登頂した。しかし下山中3名が遭難しかけた。
予告編
あらすじ
植村直己の大いなる冒険は23歳の時に始まった、植村の全財産は110ドル(4万円)、他にあるものといえば、若い精神と肉体、そして大きな夢だった。植村はこの放浪時代に、いかなる困難、苦労にもめげず、誠心誠意の体あたりで、やりたいことを次々に実現した。モンブラン、マッターホルン、レナナ峰(ケニア)、キリマンジャロ、アコンカグアを単独で登った。

そしてアマゾン川 6000キロを筏で下ることまでやりとげた。1970年5月には、日本人として初めてエベレスト山頂に立った。そして3ケ月後には、北米最高峰マッキンリー単独登頂に成功。5大陸最高峰すべてを征服する記録を打ちたてた

1973年、グリーンランドで犬ぞりの訓練をしていた植村直己が日本に一時帰国した。彼は馴染みの店の近くに住んでいる野崎公子という女性に出会い、心を惹かれる。彼は公子に自分の書いた本を手渡す。公子は本を読み、植村直己について知る。
植村は大学時代、優れた登山家である友人の小川に連れられて初めて雪山登山に挑んだ。そこでの失態を恥じた彼は、猛トレーニングを開始した。4回生の時、小川のアラスカでの経験を聞いた村は、海外への憧れを強く抱くようになった。
植村は就職もせず、海外へ飛び出した。フランスでアルバイトをしていた彼に、小川達のグループからヒマラヤ登頂の誘いが来た。第一次アタックに失敗したグループは、元気の残っている植村を第二次アタックに挑ませる。植村は期待に応え、登頂に成功した。
その後は単独での登山を続け、植村は五大陸の最高峰単独登頂に成功。彼は目的を山から極地へと転換する。1974年、公子と結婚した植村だが、冒険への意欲は全く衰えることが無い。

1978年3月5日、植村直己は51日間の苦難と死線をさまよう北極点単独行に出発した。恐らく2度と誰も成し得ないだろうといわれる世紀の大冒険である。文明国の冒険家は、その資力にものを言わせて、エスキモーと犬橇を大量に従えて氷原に乗り出したのだが、それでも北極点に立つことは容易ではなかった。植村はそれを、たった一人で決行し成功したのだ。マイナス 50度を越える寒さとの戦い。白熊の襲撃。逃げたエスキモー犬。開氷面に包囲される恐怖。クレバスへの転落。食糧の欠乏。何日も孤立させる死のブリザード。1日5キロも進めない乱氷原そして数々の誤算。植村と犬が互いにはげまし合い、ともに戦って苦難の道程を進む様子は、まさに地獄絵図であった。
結末
彼の冒険熱は失せることなく1978年4月29日に、植村直己は苦難の踏破を成功させた北極点に立ち、日本、カナダ、デンマークの国旗を立てた。そして、文字どおり生死を共にした傷だらけのエスキモー犬の一頭一頭を抱き、労をねぎらう言葉をかれた。犬たちにも植村の気持が通じている。心から嬉しげに尾を振ってくれた。植村は泣けて泣けてならなかった。あせり、怒り、絶望し、奮起し、そして成し遂げた前人未到の記録であった。彼は南極大陸を犬ぞりで横断する計画を立てるのだが…。

植村の最後の目標は、彼の10年間の夢である南極だった。南極は植村にとって残された最後の大冒険になるはずだった。

1984年2月13日午前11時、マッキンリー冬期単独登頂に成功した、との交信を最後に植村の消息は断たれた。懸命の捜索にもかかわらず発見されず、絶望を認めないわけにもいかなくなった。
日本政府は、植村直己の輝かしい業績に対して、彼の死亡が確定的になった1984年4月19日に、「国民栄誉賞」を贈った。
ラストに記者会見が開かれ、公子夫人は「私は、死んでいるとは思っていません。あの人は、常々申しておりました。冒険で死んではいけない。生きて戻ってくるのが絶対、何よりの前提である」と述べるのであった・・・